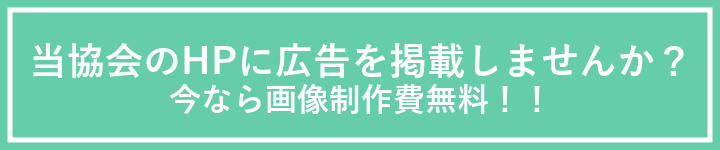シャルトル大聖堂
ある日、広島空港発お手軽フランス旅行の中に「シャルトル」の名前を発見。「磯崎新の建築談義」全12巻の第6巻目であるゴシック建築の代表として上げられている「シャルトル大聖堂」のことである。旅程を読んでみると、世界遺産のモン・サン・ミッシェルも見られるし、パリ市内の自由時間も組込まれている。ただし中国東方航空便なので、往き帰りが上海経由となっている。でもこれは願ったり叶ったりかもしれない。急激な開発が驀進する旬の上海を観光出来るというのは。日頃、私が愛用しているグーグルアースの空中散歩を傍目から毛嫌いしている奥さんも観光旅行となると大賛成である。さっそく申込み、代金も振込んだのになかなか資料が送ってこない。出発前1週間を切って、やっとそれが送られて来た。最小催行人数を新婚さんの2組を含めてやっと1名オーバーしたのだという。広島空港のテリトリーはかくも小さいものだと、あらためて恐れ入りました。
ゴシック建築とは何か。ロマネスクとかルネッサンス建築は何となく馴染みやすく好感が持てるのですが、ゴシックとかイスラム、ビザンチンは違う世界の建築として敬遠してきたきらいがあります。ゴシック建築は12世紀の中頃、フランスで発達。そして前代のロマネスク建築をいくらか上回る範囲のヨーロッパ地域に広がり4世紀にわたって栄えた。ゴシック大聖堂の奇跡に近い構造は、重力に抗してものを建てようとする人間の絶え間ない努力の結果として成し遂げられた。なぜこのような要望がおこったのか。中世の宗教の力でしょうか。ゴシックの行き過ぎた垂直性を嫌い、また飛梁、控え壁をとりわけおぞましく感じる人もいる。足場がまだ現地に取り残されているように見えて、不安定で醜悪であると。けれども教会堂を建てた人々は飛梁、控え壁を恥とは考えなかったはずだし、それらを大聖堂の周りで勤務中の巨大な衛兵たちと見なした。

1983年頃発行された「建築行脚6凍れる音楽 シャルトル大聖堂」に掲載された「南東の塔」の写真。よく見ると、建築家の磯崎新(左側)と写真家の篠山紀信(右側)の姿がさりげなく挿入されている。撮影者は助手のカメラマンか? 町並みがはるか眼下に望まれる。逆に見れば、巡礼者達はこの大聖堂をはるかかなたから仰ぎ見ることができた。学問で知られるこの地に、シャルトルの偉大な師の教えを求めて学生達が集り、真実と美、時と永遠性に静かに耳を傾けた。

建築作品としてのシャルトルは、同時期に建てられたランス、アミアンなどの大聖堂には及ばない。しかしシャルトルには、それらのいずれよりも優れた彫刻やずっとすばらしいステンドグラスがある。ゴシック芸術の総合体として見ると、シャルトルは群を抜いている。人間の創った最も美しい芸術品の一つといってよい。ラテンクロスの平面になったロマネスク様式の大聖堂が創られたのは1028年頃である。この大聖堂は西、北、南の各面に、すべて3扉口を持っている。扉口に飾られた石灰石彫刻群の中にはフランス美術の最高傑作とされるものがいくつか含まれている。また176の窓があり、それらの大部分は13世紀以来のもので、今なお中世のガラスをとどめている。ヴィクトリア期の美術評論家ジョン・ラスキンが「燃え上がる宝石群」と呼んだステンドグラス群がここにある。

<西正面>
左の華麗な北尖頂屋根、後期ゴシックで1507年頃付加。高さは115m。右の南塔は12世紀、初期ゴシックのもの。美しくすっきりした八角錐の尖頂屋根を持つ。高さは106m。左右で時代、様式、高さがちがうというゴシック建築の特質、オープンシステムの良さが表れている。
13世紀頃のシャルトルはまた重要な商業の中心地としても栄えた。そこで商人組合はこの大聖堂のために42の窓を献納した。政治、宗教は勿論の事、商業にまつわる当時の日常生活などの様子をステンドグラスの絵柄によって窺い知る事が出来る。現地ガイドの日本人からそれらの多くを興味深く解説して貰った。彼はシャルトルに住み、十数年解説しているが、尽きない魅力があるとのことでした。

<南玄関>
1210年∼1225年頃の建設。眼を見張る彫刻群が配され、三連の覆いかぶさるように深い扉口をもつ。両側に計画された双塔は未完である。バラ窓と五連のランセット窓。内側から見ると華麗なステンドグラスも外観では石造に類似したくすんだ配色の窓ガラスにしか見えない。

<北立面>
身廊の大アーケード上方に、側廊屋根裏を隠すギャラリーとしてトリフォリウムをつくり、対になったランセット窓と小バラ窓がついた。3段になった飛梁と巨大な控え壁によって壁面を解放し、ステンドグラスを多用することが可能となった。

<北玄関/フランス王家のバラ窓>
中央に聖母が幼児を抱く。放射する花弁には、精霊をあらわす鳩と天使。大聖堂のステンドグラスは20世紀の二度の世界大戦の時、取り外され他所に保管されたので無傷のままであったといわれている。その方法を聞き漏らしたが、雨仕舞いに関わるものだけに、その苦労の大きさが偲ばれる。
1757年に起工されたパリのパンテオンは新古典主義の建築家ジャック・ジェルマン・スフロの設計です。彼はゴシックの研究をして、柱をぎりぎりに細くし、壁もはずして外からの光を入れようとした。しかしやりすぎて全体の構造が危なくなり、壁をあわてて追加したそうです。
19世紀になると、ヨーロッパの各国でゴシック・リバイバルが起きました。そしていろいろなゴシック論が出て来ます。イギリスではジョン・ラスキンやピュージンに代表される倫理的な解釈。フランスではヴィオレ・ル・デュクの合理的な解釈。ドイツではW・ヴォリンガーやカール・フリードリヒ・シンケルらの民族性に訴えるものなどがありました。いずれも建築そのものの分析というよりも、強いイデオロギーを反映したゴシック論ですが、次の時代の近代建築へと続く考え方を先取りしたものとして評価されています。
かくのごとく、ゴシック建築の精神は「パリのポンピドーセンター」のような「ハイテク建築」として姿を変え、現代にも生きているというのが「磯崎新の建築談義」第6巻での貴重なひとことでした。そして篠山紀信のカメラワークにも今更ながら驚嘆するものを感じたお手軽フランス旅行となりました。今回、カメラ(Nikon-N200)とディスク(3G-1000枚用)を携帯したのですが、結果的には500枚ぐらいしか撮れませんでした。篠山さんは1日当り500枚ぐらい撮影すると聞きました。桁違いとまではいきませんが、さすがプロですね。
2008.1.31 – 日高卓三
この記事は旧エキサイトブログ「室内気候」にて人気だったエッセイを再編集したものです。
投稿日と執筆日では年数が離れていることをご了承ください。
編集:北村